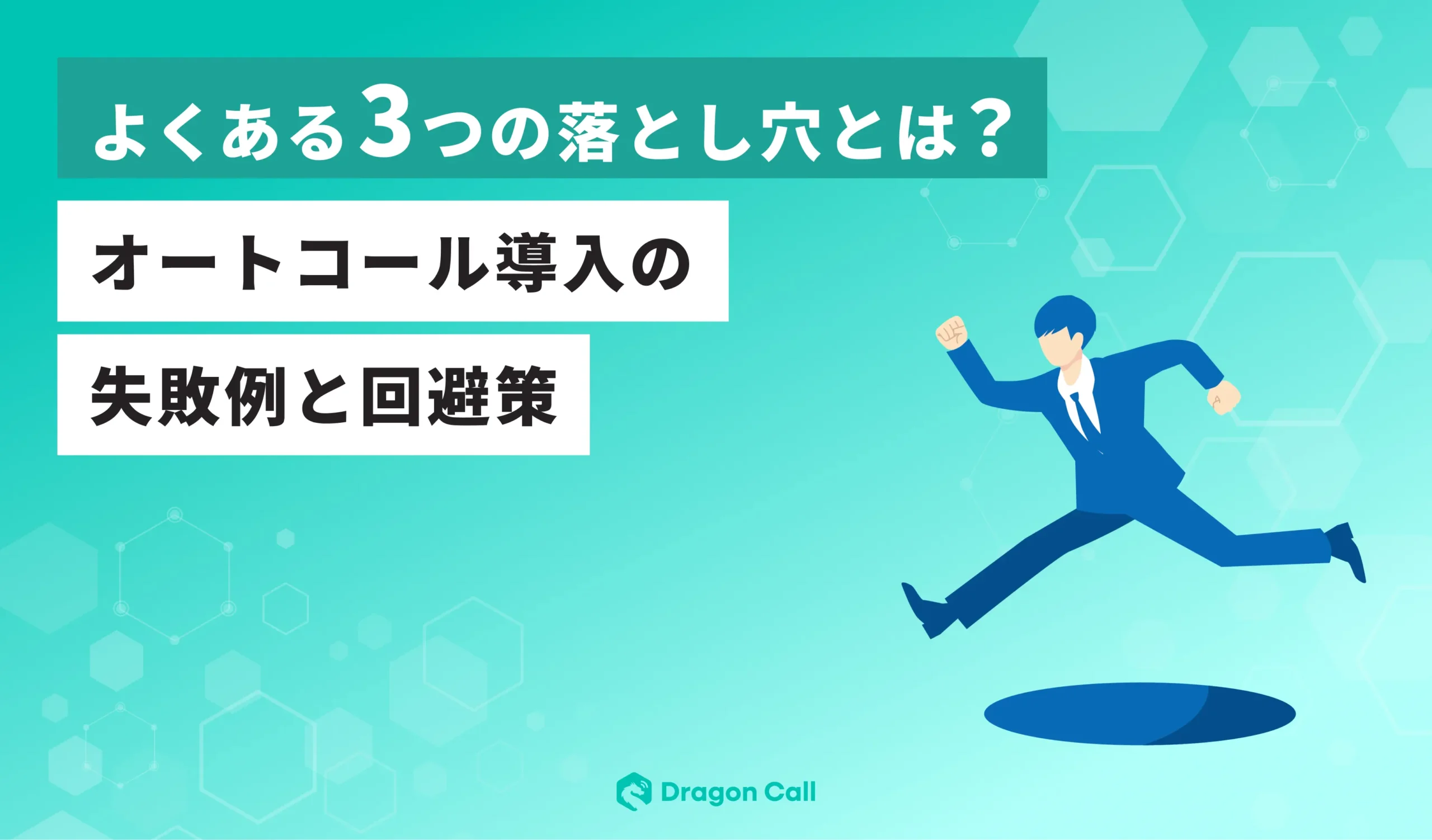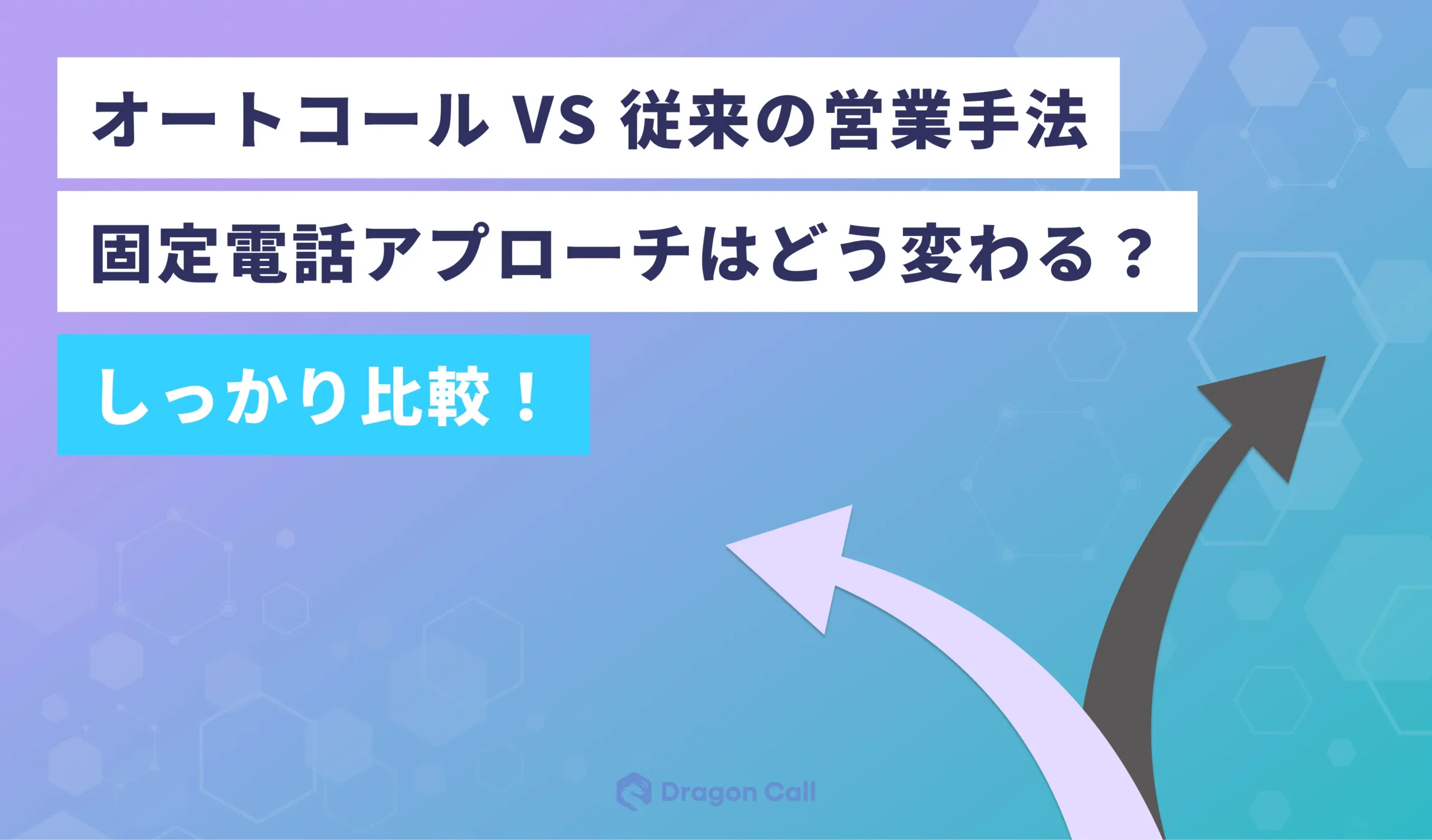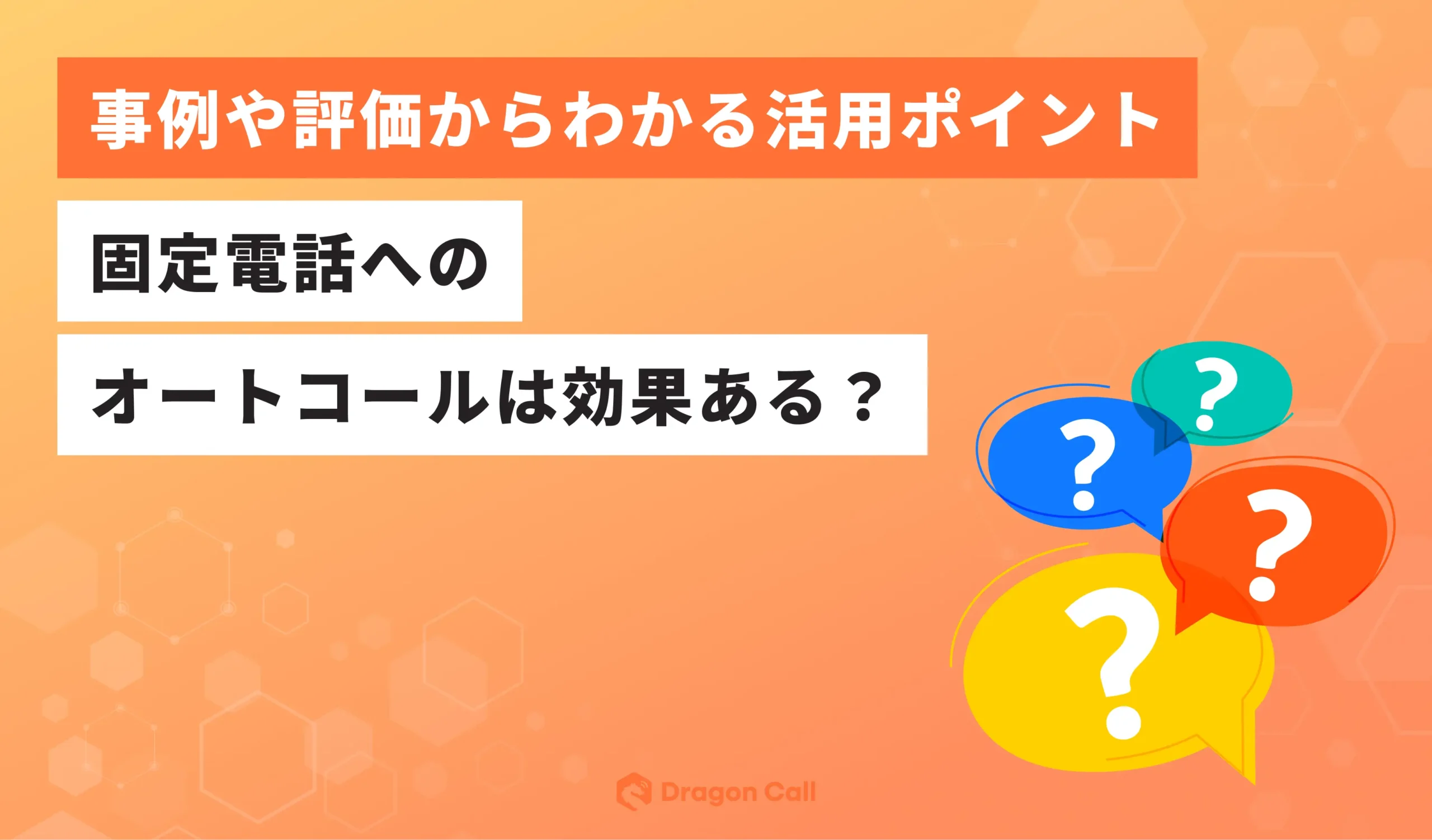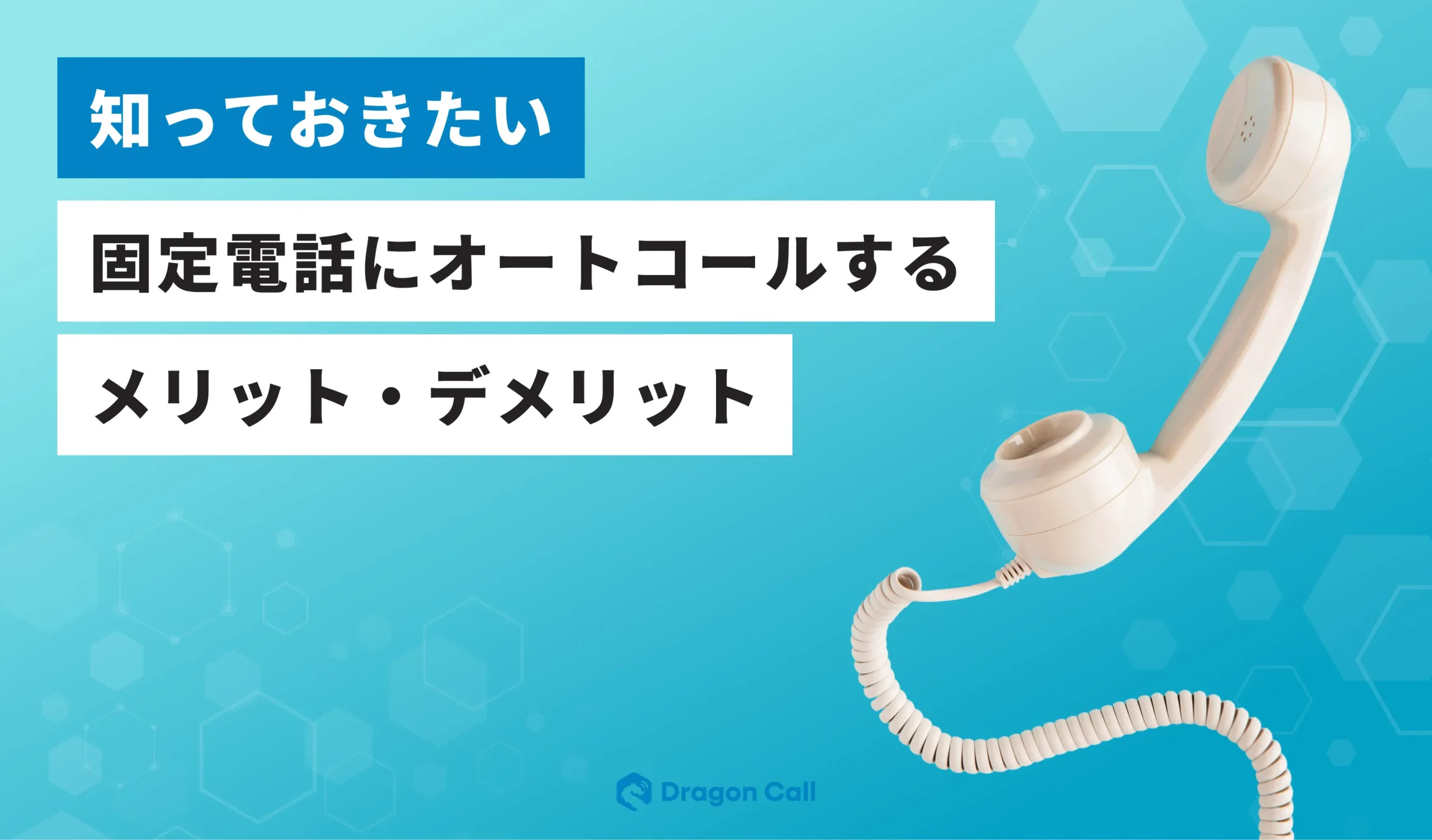そもそも、オートコールってどんな仕組み?

1. オートコールとは何か?

オートコール(自動発信、オートダイヤリング等とも呼ばれる)は、 あらかじめ登録した電話番号に対して、音声メッセージを自動で発信するシステムを指します。録音済みの音声や、TTS(Text To Speech:テキスト読み上げ合成音声)を使って案内を流すのが一般的です。
また、IVR(音声自動応答)機能と組み合わせることで、受け手が電話を取った際に「1 を押す/2 を押す」などの操作を受け付けるケースもあります。
つまり、オートコールは「有人オペレーターが1件ずつ電話をかける」従来の方式を省力化・自動化するアプローチといえます。
2. オートコールの仕組みを分解して理解しよう
オートコールを導入する際には、内部でどのような流れがあるかを理解しておくと、運用やトラブル対応もスムーズになります。次のような要素・ステップが一般的です。
- ①発信対象リストの準備
- 電話番号や属性(顧客名、予約日時等)をまとめたリストを作成します。
- ②メッセージ/音声コンテンツの設計
- 録音済み音声、または TTS による音声案内文を設計します。
- シナリオ(複数分岐など)がある場合はフロー設計も行います。
- ③発信スケジュール設定
- 発信時間帯や間隔、リトライ回数などをあらかじめ設定します。
- ④自動発信処理
- システムが登録リストに対して自動的に電話をかけ、設定したメッセージを流します。
- ⑤応答処理(IVR処理)
- 受け手が応答した場合、「1を押す」「2を押す」などのプッシュ応答を受け付けて処理します。
- ⑥通話ログ/レスポンス収集
- 通話の成功/失敗、応答内容、発信時間、応答音声などをログ取得し、集計・分析に利用します。
- ⑦フォローアップ
- 応答のあった相手についてはオペレーター転送、SMS送信、再発信など追加アクションを起こします。
このようなステップを通じて、オートコールは“ただ音声を流すだけ”の装置ではなく、応答を受けて流れを分岐させられるインタラクティブなツールとして機能します。
3. オートコールが使われる代表的な業務

実際、どんなシーンでオートコールが活用されているか、よく見られるケースをいくつか紹介します。
リマインダー通知(予約確認・来店案内など)
病院、クリニック、美容室、飲食店、士業など、予約が関わる業種で使われることが多いです。来店前日に自動電話で確認を行い、無断キャンセルを減らす目的で利用されます。
一斉通知・安否確認
災害時の従業員の安否確認、学校・自治体等での緊急通知などで効果を発揮します。多数の対象者に短時間で連絡を取る必要があるケースで向いています。
顧客アンケート/満足度調査
通話形式アンケートを実施する際、オートコールを活用すれば高齢者などインターネットが苦手な顧客層にもアプローチできます。応答結果は自動集計できます。
営業フォロー・テレアポ代替
資料請求後フォロー、定期案内、既存顧客への販促案内、休眠顧客掘り起こしなど、定型的な伝えたい内容が決まっている業務で使われます。
督促・請求案内
支払督促・期日案内など、忘れ防止目的でオートコールを使うケースも増えています。
4. オートコール導入のメリット
導入によって得られる主な利点を整理しておきます。
大量同時発信による時間効率化
一度に多数の相手に発信できるため、オペレーターが個別にかけるより大幅にスピードアップできます。
応答率の向上
電話は到達性が高く、目立ちやすいアプローチ手段です。反応率向上に寄与します。
対応品質の均一化
録音や定型メッセージで発信することで、オペレーターによるばらつきを排除し、常に一定の品質で伝達できます。
オペレーター負荷の軽減
定型的な発信業務を自動化できるため、オペレーターはより付加価値の高い業務に注力できます。
コスト削減
長期的には人件費や時間コストの削減につながります(ただし導入費・運用コストとのバランス検討が必要)。
レスポンス管理/ログ活用
応答内容、実施結果、通話ログをデータとして蓄積でき、改善や分析に活かせます。
5. 導入時に押さえておきたい注意点・リスク
一方で、導入・運用時には注意すべき点もあります。
「自動電話=迷惑電話」と受け取られるリスク
一方的な自動発信は、受け手側に不快感を与える可能性があります。発信頻度や内容、時間帯配慮が不可欠です。
柔軟性・個別対応力の制約
あらかじめ用意したメッセージ以外の対応は難しいため、例外処理や想定外の問い合わせには対応できない可能性があります。
通話到達率・回線混雑・切断
発信先の電話番号が不通、回線混雑、通信障害などで通話に失敗するケースがあります。
着信拒否/迷惑電話規制
受け手が自動発信を拒否設定していることや、規制ルールに抵触する可能性があります。
個人情報・電話番号リストの管理
発信先リストには個人情報を含むことが多いため、安全な管理・セキュリティ体制が必須です。
運用後フォロー体制の不備
オートコールだけでは対応しきれない問い合わせ対応の体制(オペレーター転送など)を整えておかないと機会を逃します。
6. システム選定のポイント
導入するオートコールシステムを選ぶ際、比較すべき重要な観点を挙げておきます。
- ①最大同時発信数
- 一斉通知時や大規模運用を想定するなら、同時に何件発信できるかが重要です。
- ②音声品質・バリエーション
- 合成音声の自然さ、声の選択肢、抑揚調整などが導入効果に直結します。
- ③コールフロー設計機能
- 分岐、リトライ、オペレーター転送など柔軟に設計できることが望ましいです。
- ④料金体系
- 月額固定、従量制、初期費用、最低利用期間、通話単価などを総合判断する必要があります。
- ⑤通話録音・ログ管理
- 通話記録を残す機能、ログ閲覧・ダウンロード機能、レポート機能の有無。
- ⑥運用サポート体制
- 導入支援、コールフロー設計サポート、トラブル対応などのサービス体制。
まとめ
オートコールは、定型的な発信業務を自動化し、人的コストの削減や高速対応を可能にする強力なツールです。一方で、受け手視点での配慮や柔軟な対応設計、システム選定のポイントをおさえないと逆効果になる可能性もあります。
「自社業務のどの領域にオートコールを導入すべきか」「どのような応答設計が顧客体験を損なわないか」など、戦略設計が成功の鍵になります。当社のオートコールシステム Dragon Callは、こうした課題を意識した設計・サポートを行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。